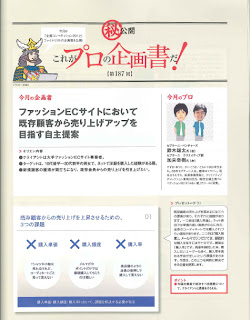2012年を振り返ってみて、、、
とにかく楽しかった.(o´∀`o)!
とにかく楽しかった.(o´∀`o)!
さしずめ、小学生の読書感想文のような表現だけれど、
仕事も楽しかったし、プライベートも充実していた。
もちろん大変なこともあったし、ダークサイドが垣間見えた瞬間もあるけれど(笑)
楽しいことが多くて、バランスシートはプラスに大きく傾いている。
小さい時には、大っ嫌いだったマラソンなのに、
今年だけで、合計6個の大会に参加している自分に驚く。
「マラソンは単なるカロリーの浪費で、拷問の一種だ」 と罵っていたはもはや過去のこと…。
Mr.children
デビュー20周年の今年。
1年に3回もミスチルのLiveにいける年なんて、
これからの人生でもうないかも知れない。
ミスチルのLiveは、最高の幸福感と前向きな気持ちをくれる、僕の人生のガソリンです。
旅行
今年は、社員旅行が2回あったことも合わさって、
大学生のようなペースで旅行した。
大学生のようなペースで旅行した。
美ら海水族館(沖縄)旭川動物園(北海道)大地の芸術祭(新潟)地中美術館(香川)。
北から南まで、動物園、水族館、美術館を回った1年だった。
北から南まで、動物園、水族館、美術館を回った1年だった。
OVERVIEW 2012
3月
(マラソン) 大島マラソン(42.195Km)
(マラソン) サイパンマラソン(21.0975Km)
年代別6位入賞 !(実力ではなく、参加者少なかったため(笑)
4月
(仕事) ベストマネージャ賞 受賞
5月
(マラソン) 軽井沢マラソン(21.0975Km)
(旅行) 沖縄(社員旅行)
念願の美し海水族館!
(Live) Mr.children TOUR POPSAURUS 2012
6月
(仕事) 社内新規事業コンテスト 準優勝
7月
(Live) ap bank fes'12
Mr.children、Spitz、Salyu、最高でした。
08月
(Live) ROCK IN JAPAN
YUKI、マキシマム ザ ホルモン、PRINCESS PRINCESS、秦基博、最高でした。
(旅行) 瀬戸内海(直島・豊島)
念願の地中美術館&豊島美術館、最高でした。
09月
(旅行) 大地の芸術祭(越後妻有)
(旅行) 恒例の牧場ツアー(日光・宇都宮)
(仕事) Yahoo! JAPAN インターネット クリエイティブアワード 2012ノミネート
受賞ならず!
(旅行) 八ケ岳
念願の星のリゾート!
(仕事) 販促会議企画コンペディション ゴールド受賞
10月
(仕事) 転籍
広告代理事業の営業マンから新規事業プロデューサーに職種変更
(マラソン) 伊平屋ムーンライトマラソン(沖縄)(21.0975Km)
11月
(旅行) 北海道(社員旅行)
念願の旭山動物園!
(マラソン) 富士山マラソン(17Km)
12月
(マラソン) ホノルルマラソン(42.195Km)
キラウエア!マウナケア!ラニカイ!ワイキキ!
去年より1時間半もタイムが縮まった!
(Live) ももいろクローバー ももいろクリスマス2012
昨年までは好きではなかったのに、、今年どっぷりハマってしまった。
(Live) Mr.children (an imitation) blood orange] Tour
今年の締めくくりに相応しい最高のライブ!
楽しいことが、本当に多かった1年だった。
ホノルルマラソンやMr.childrenのライブという大きなイベントが最終月の12月にあったのが、
2012年を魅力的に見せている要素もあるけれど、
それでも、総じて 「あー楽しかった!」 と思って年の瀬を迎えられるのは幸せです。
いまから年末最後のイベントとして、スノボに出かけてきます。
(最後の最後に怪我をしないように、気を付けないと)